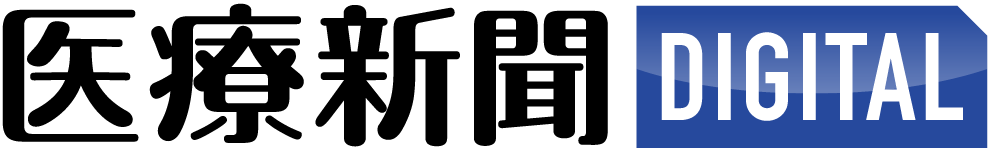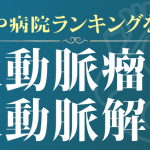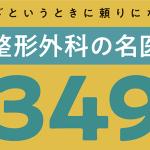投稿日: 2016年7月10日 1:20 | 更新:2016年11月2日12:12
独立行政法人 国立成育医療研究センター
器官病態系内科部 消化器科医長 新井勝大
■「これまで見えなかったもの」が見えてきた

小児の炎症性腸疾患の中でも、小腸の小さな病変は見つけるのが難しく、発熱や下痢、腹痛などの症状があるにも関わらず、検査をしても明らかにできないケースがありました。しかし、カプセル内視鏡で検査すれば、びらんやアフタ潰瘍など、造影やCTではなかなかわからなかった粘膜表面の浅い潰瘍も見つけることができます。
私たちは、炎症性腸疾患の子どもたちを診ることが多いのですが、最初の診断の時点からカプセル内視鏡を積極的に使うようになりました。今年は年間で30件を超える勢いです。少なくとも、私たちの施設では、小腸を診断する際のスタンダードな検査と位置付けています。
■適切な診断ができ、治療の適正化に大きく貢献
カプセル内視鏡を導入して、適切な評価ができることで「どこまで治療すればいいか」という治療の適正化が図れるようになりました。クローン病が長くなると、潰瘍が瘢痕化するケースがありますが、適切に活動性が評価ができるので一歩進んだ治療を行うことができます。
こういう例もありました。5~6年間、原因不明の貧血・下血という症状があり、かろうじて生活が維持できているという状態の男子(10歳)です。しかも、開腹歴があったため、外科の先生も手術をすることに躊躇されていました。そこでカプセル内視鏡検査を行ったところ、小腸に活動性の潰瘍があることがわかりました。それまでの検査では見つけられなかった病変です。結果的には開腹手術を施しましたが、適切な診断のもと、タイミング良く手術できました。今では貧血も改善し、元気に学校に通っています。子どもの場合、その病気と長い間付き合わなければならないこともありますからね。病気の発見がQOLを向上させて、お子さんの人生を変えてあげられた例だと思っています。
■診療をサポートしている機器の進化
10歳以下のお子さんだと、自分でカプセルを飲みこめないケースがあります。かつては、胃の中に送りこんだカプセルをスネアでつかんで十二指腸まで運んでいたのですが、今では内視鏡の先端に取り付けた補助具にカプセル内視鏡を装着、十二指腸まで送りこんだところでカプセル内視鏡を切り離すことができます。十二指腸までいけば自然に流れて進んでいきますから。この補助具のおかげで、飲み込めない小さな子どもたちへの検査も容易にできるようになりました。とても助かっています。
あとは、パテンシーカプセルですね。カプセル内視鏡が詰まってしまうと、場合によっては手術を‥と心配されますが、「同じ大きさのカプセルが小腸・大腸を通ってちゃんとお尻から出てくること」を前もって確かめられるので、今では安心して検査を勧めることができます。
■小児にも炎症性の腸疾患は増えている
クローン病や潰瘍性大腸炎患者のおよそ25%は18歳未満で発症しますが、その数は増加傾向にあると思います。生後数週間の乳幼児でも、これらの炎症性の腸疾患だったケースがあります。原因ははっきりとはわかりませんが、食生活の変化や腸内細菌叢の変化によるという説もあります。小児全体でアレルギー疾患が増えていることを考えると、免疫的な要因が増えているのかもしれません。
■子どもたちのQOLと未来を変える
いま、小児科でカプセル内視鏡を採用している施設は全国で10~20施設、少しずつ増えています。小児のカプセル内視鏡やバルーン内視鏡に特化した研究会も立ち上がって活動を始めています。関連学会でも演題が増えてきました。
カプセル内視鏡によって、出血の原因がわからず、またCTやMRIでも見えなかったものが見えるようになりましたし、パテンシーカプセルの登場により滞留の問題も解決できました。読影に際しては、成人の症例画像と着眼点が異なるため注意が必要ですが、小児であっても小腸の評価ができる時代になっているので、小児科でも積極的に取り組んでほしいですね。その子のQOLや未来をも変えることができる、画期的な検査だと思いますから。