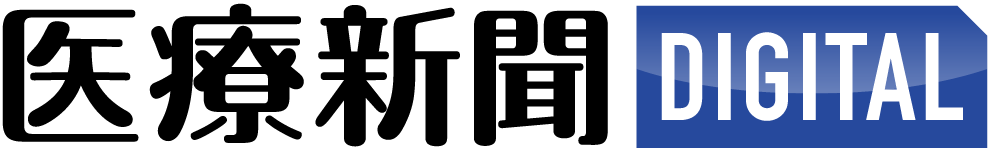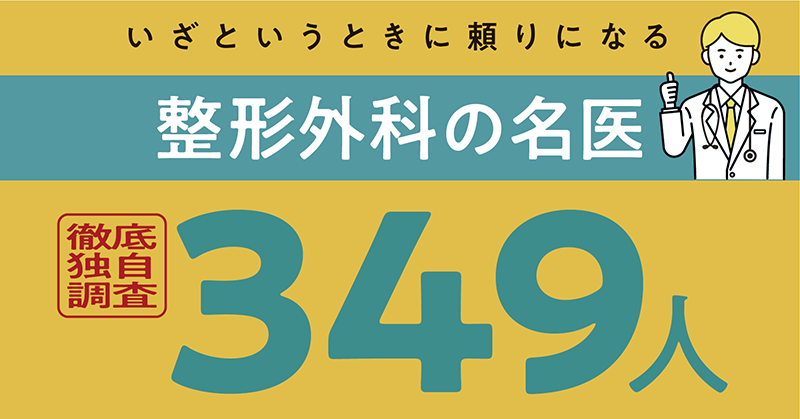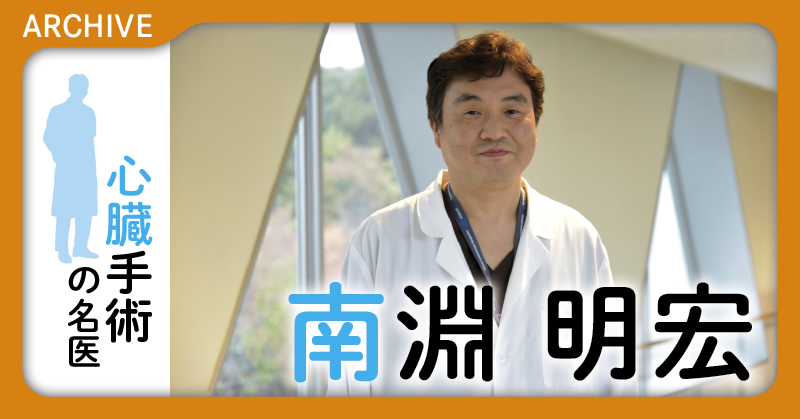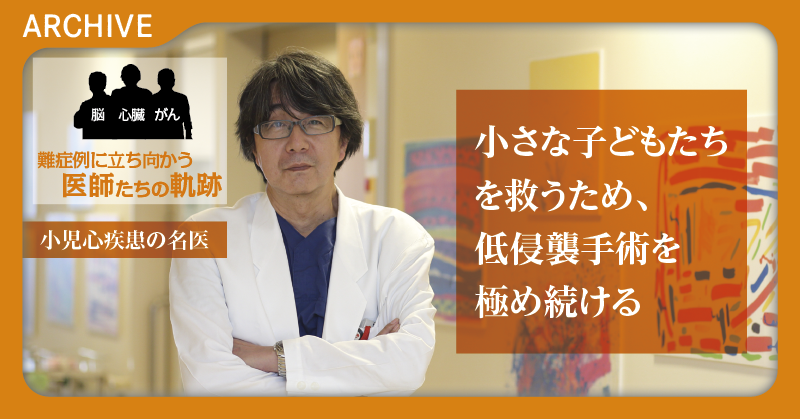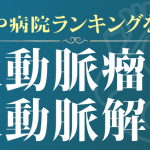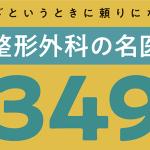投稿日: 2017年3月8日 9:00 | 更新:2024年1月19日14:44

モットーは「細心と革新」ベストな手術を追及し続ける
1994年、それまで不可能とされていた肝臓の最も奥深い部位を単独で切除する「尾状葉単独全切除術(高山術式)」を世界で初めて成功させた高山忠利医師。肝がんの手術数で全国第一位を誇る肝がん治療のトップランナーだ。
■取材
日本大学医学部 消化器外科教授
高山 忠利 医師
──医学の道、なかでも消化器外科という分野をなぜ志したのですか。
高山 医学を志したのはひとえに父の刷り込みです。父は若い頃、医師を志していましたが、家業を継ぐために諦めざるを得なかった。それで私に将来、地元でクリニックを開業させようと思っていたようです。
長男である私に父は医師の夢を託しました。そして私もいつしか医師を目指すようになり、医学部へ進学しました。開業医志向の私でしたが、20代後半、国立がんセンター中央病院で任意研修の際に、恩師となる幕内雅敏先生との運命的な出会いがあり、その肝臓手術に大変感銘を受けました。
研修終了後、地元で開業の準備をしていたところへ、何と幕内先生から「うちに来ないか」という電話が。それはびっくりしましたよ(笑)。ただちに大学を辞めて国立がんセンター中央病院に転勤。その後は東京大学、そして現在の日本大学板橋病院と、一貫して肝臓外科医の道を進むことになったのです。
──有名な「高山術式(尾状葉単独全切除術)」は、どのようにして行われるようになったのでしょうか。
高山 1993年、当時勤務していた国立がんセンター中央病院で、一人の患者さんの肝がんが、肝臓の一番深く奥の部分である尾状葉に位置しており、前面から目視することができなかった。いわゆるアンタッチャブルな状態で、その場所にがんがあったら手術はできないと言われていた部位でした。
尾状葉切除は、周辺部分も含めて大きく取れば不可能ではありません。しかし肝硬変などがあると、肝臓を大きくは取れない。したがって尾状葉を単独で取ることはできないとされていたのです。今でこそ出血は少なく済むようになっていますが、当時は肝がん手術の術式が確立されておらず、それこそ平均出血量が5000㍉リットルという時代。そのなかでもがんセンターの肝臓グループだけはその5分の1程度の出血しかない、綺麗な手術でした。
実はこの2年前、母校である日本大学病院で尾状葉切除を初めて行いました。このときは区域7の診断でしたが、実際に切除してみるともっと深く、区域1(尾状葉)にあった。もともと「区域1なら手術しない」とされていましたから、国立がんセンターで診断していれば初めから手をつけていなかったはずでした。手術でも何でも「一番が最も大事」とされるのは、一回やってしまうと、その後の心の余裕が全然違うからです。
そういうことで、93年の国立がんセンターでの症例は、私にとっては二例目。患者さんは肝硬変を併発しており、大きく切除できない状態でしたから、区域1だけを意識して切除することにしました。そして無事に単独切除は成功。さっそく「高山術式(尾状葉単独全切除術)」と名付け、この手術に関する論文をアメリカの医学誌に提出したのですが、当時は掲載まで1年かかる時代。この間、私は誰にも秘密にしていました。ええ、幕内先生にも(笑)。掲載時期を確認して学会で発表したのですが、その時の座長が幕内先生。そこで「画期的だね」と言われました(笑)。それが最初で最後の誉め言葉でしたね。

1995 年に幕内グループの一員としてフランス・ストラスブルグでの国際学会に参加(後列の一番左が高山医師)
──後進の育成や技術の継承などについてはどのようにお考えですか。
高山 指導に関して、私は基本的に質問されれば答えはしますが、こちらから手取り足取り教えることは一切ありません。幕内先生はもっと極端でした。研修医の頃、疑問点を先生に聞いたところ、知らん顔をされました。それ以来20年近くのお付き合いのうち、質問したことは1回もありません(笑)。
何年もかけて苦労して獲得したテクニックを、そう簡単には教えられませんよ。その代わり、後ろでズーッと見て、自分でノウハウをつかむ。その方が勉強になるのです。隠さずに見せてくれるわけですから、それで十分。それ以上頼るようでは外科医として一人前ではない、少なくとも新しいものが創造できないということです。私たちは技術者、職人なのですから。
──手術をするか、他の治療でいくかの判断基準は。
高山 がん治療の評価項目は生存率以外にありません。現在、手術による治療では、5年生存率は全国平均57%です(当院は63%)。30年前はわずか20%でしたから、実に大きな進歩です。対して2000年頃から始まったラジオ波焼灼療法(RFA)は58%、肝動脈塞栓療法(TAE)はもともと進行性がんを相手にしているので26%です。このように、単独の治療では手術が一番であるものの、肝がん患者全体の3割にしか施行されません。残り7割は肝硬変がひどくて手術を受けられない方、末期がんの方なのです。
さらに手術の対象は肝機能の良い方ですから、成績が良いのは当たり前。RFAやTAEはもっと進行した肝がんや肝硬変を対象にしていますから、同じ治療のパワーがあっても、成績が下がるのは当然なのです。ですから、各治療法の良い悪いについて論じるのではなく、それぞれ守備範囲が違うということ。これら3つをうまくコーディネートすることで、全体として肝がん治療が底上げされるのが一番良い形なのです。その意味では、日本は世界で最も良い成績を収めています。
肝がんは自覚症状がなく、早期診断が困難ですが、毎年超音波検査を受け、2㌢位の状態で見つけて切除できれば、5年生存率が胃腸がん並みの全国平均80%に到達しています。そのカギを握るのは早期発見です。
────現在目指していること、注目していることについて教えてください。
高山 やはり術式の確立になるでしょうか。「どのような手術がベストなのか」は私の最大のテーマですが、実はまだ証明されていません。証明にはランダム化比較試験が必要で、そこでデータをきちんと示せれば、私自身が35年肝臓手術をやってきた意味があると思っています。
さまざまな手術を開発されてきた幕内先生も、その手術が諸外国を含めた他の術式と比較して本当に良いのかという検討は十分ではありません。私たち弟子は、その証拠を示すのが大きな責務だと考えています。まあ、5~10年くらいはかかるのでしょうが。でも本物の仕事は10年くらいかかるものです。外科医を40年やって、真に有意義な良い論文が出てくるのは4本程度だと思っていますから。
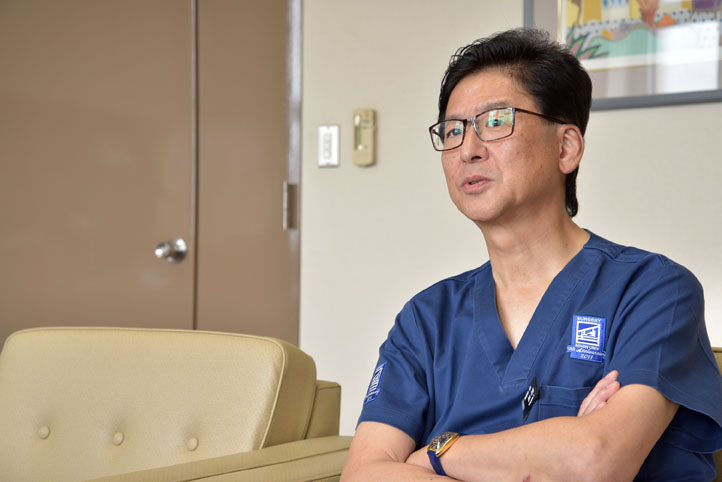
──「優れた医師」になるために必要な資質とは。
高山 今の学生は、良くいえばスマートなのだけれど、淡白すぎる傾向がありますね。泥臭さがないように思います。あくまでも患者さん中心という気持ちでいないといけません。私たちは命を預かる究極のサービス業ですからね。
100人学生がいた場合、外科には2、3人しか来ないです。理由を聞くと、「あんなきつい仕事はしたくない」。医師の数そのものは厚生労働省が増やしているのに、実働が少ないので、全体的には医師不足なのです。入学試験を再考する必要があるのかなとも思います。
──信頼できる医師や施設を探す際に注目すべき点について、どのようにお考えですか。
高山 手術件数が最も重要で信頼性の高い情報だと思います。そしてあえて言えば、プラス手術死亡率。外科手術であれば、それに尽きます。術後の生存率は算出方法があまりにも多く、意外に誤差が大きいのです。手術数が多くても死亡数が多ければ意味がないし、死亡数ゼロでも手術数が少なければ、それは単にやさしい症例を扱っただけということになります。手術数が多くて手術死亡率ゼロが理想。昔の幕内外科みたいなものですよ(笑)。