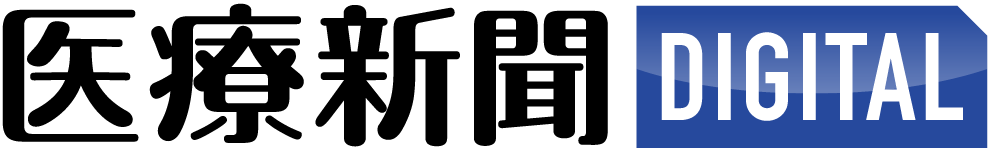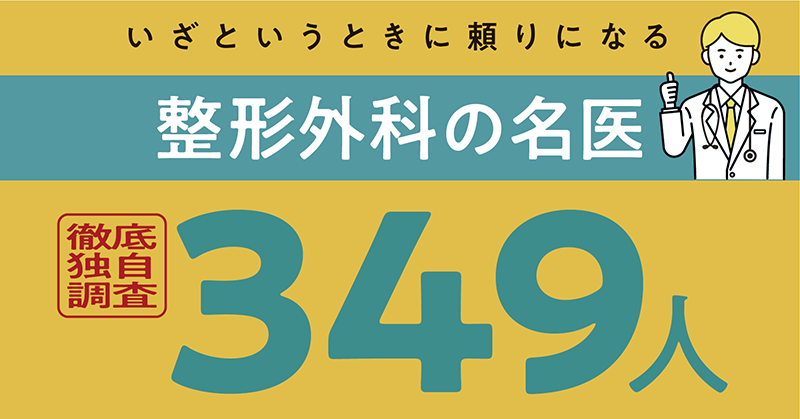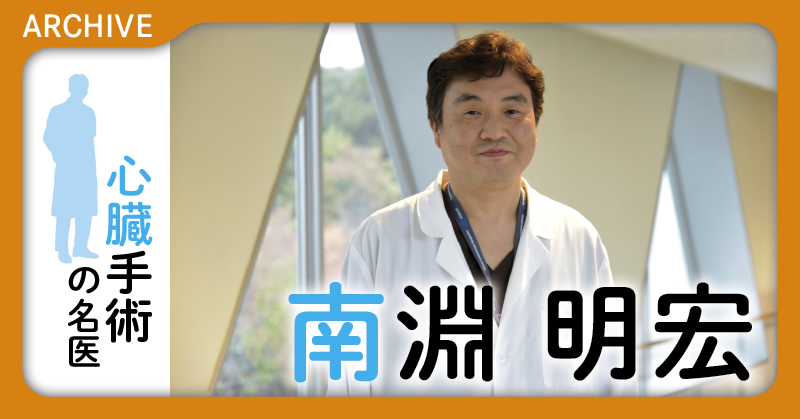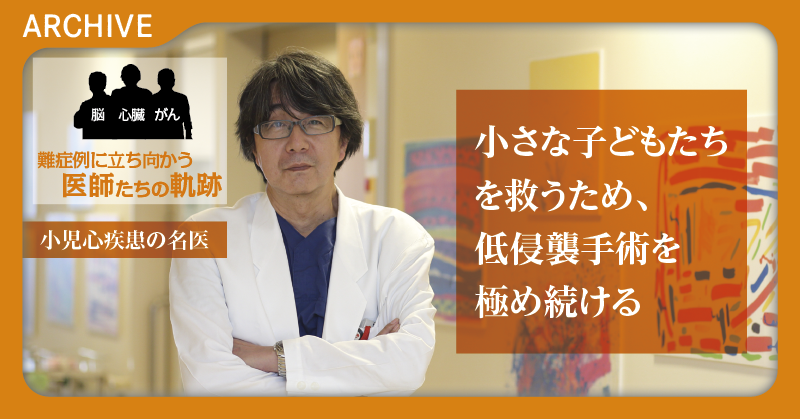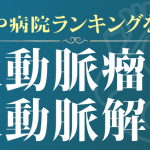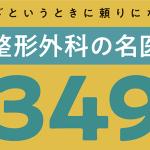投稿日: 2017年3月1日 9:00 | 更新:2024年1月19日14:45

身をもって示し、他が追従する
そういう「革命」を起こしたい
日本人のがんによる死亡原因第一位である肺がんはいまだ増加傾向にある。年間200例以上の肺がん手術をこなし、糖尿病や心臓病を抱えるような難手術にも積極的に取り組んできた鈴木健司医師。我が国の肺がん治療を牽引する肺がん手術のスペシャリストである。
■取材
順天堂大学医学部 呼吸器外科学講座 主任教授
鈴木 健司 医師
──医学の道、そして呼吸器外科を志したのはなぜですか。
鈴木 もともと体が弱かった自分を鍛える意味で親が剣道をやらせたのですが、師匠がとても厳しい人でした。幼少期のそうした体験は、自分の人格形成に大きな影響を与えるのだなと、つくづく感じています。
小学校4年生のときに長嶋茂雄さんが現役を引退されたのをきっかけに、野球にはまりました。地元のリトルリーグチームに入り、ポジションはサードで、打順はクリーンアップ。当時は4年生でしたが、市内のエースである6年生の速球を軽く打てました。「打撃の神様」川上哲治さんじゃないですが、本当に「ボールが止まって見える」感覚がありましたよ(笑)。最終的には、父に「剣道と野球のどちらかを選べ」と迫られ、剣道を選びました。中学・高校に入った頃、「剣道を本気で頑張ってみるか」という気になりました。
この頃は自分が医師になるなどとは思っておらず、京都大学の工学部を志望していましたが結果は不合格、浪人生活に入ります。実は3年生で迎えた県インターハイ予選準決勝での敗戦が悔しくて、浪人最初の半年間は引きずっていました。でも、今では敗戦から何かを学ぶ貴重な経験だったと思っています。

防衛医科大学校で医学を学ぶ
大学を卒業し、当時、心臓と食道と肺、肝臓を扱う第二外科に進みました。専門を選ぶ際は心臓外科にも興味があったのですが、当時、日本の肺がん学の黎明期を支えた恩師のいる呼吸器外科に進むことにしました。また、がんセンター(現:国立がん研究センター)の尾形利郎先生が教授としていらっしゃったのも大きかったです。
──呼吸器外科医として、どのようにして技術を培ってこられたのでしょう。
鈴木 防衛医科大学校を卒業し、5年目に国立がんセンター東病院のレジデントになりました。その間、永井完治先生に大変お世話になりました。私の技術が未熟だったので半年ほど手術を見るだけの時期が続きました。そこでいろいろな手技を見て、ビデオに収録することを繰り返しました。剣道でいうところの「見取り稽古」ですね。第一段階として、重要な経験だったと思います。そして第二段階として、東病院から築地の中央病院に移りました。
90年代当時、東病院では胸腔鏡の手術が盛んで、「とにかく傷を小さく」という時代でしたが、築地に行くと全然手術が違いました。築地の伝統は「若い人に手術をさせない」こと。不思議なことに、皆がそうやって見て学び、大外科医になっているのです。私も「まずは見ていてください」と言われました。同じ肺葉切除でも風景が異なる。肺動脈、肺静脈そして気管支を切って取るのが肺葉切除ですが、その過程で血が一滴も出ません。電気メスを多用し、血管のない部位に入っていき、炎症反応もなく、患者さんは手術の翌日には元気で4日ほどで退院するのです。
当時は退院まで2週間ほどかかる時代でした。私は茫然自失となり、「これが手術なのだ」と思うのみ。患者さんに対する本当の侵襲は傷の大きさなどではなく、出血量や手術時間、剥離といった部分にあるのではないかと感じました。この時期に築地が受け継いできたDNAを刷り込まれたのだと思います。この経験が今の私のベースになっています。
──現在の取り組みやビジョン、注目していることは。
鈴木 糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞があり、透析を受けている高齢者の胸を開けて肺を取る――そのような手術をクオリティの低い状態で行えば、必ず合併症につながります。
がんセンターの技術をもってして初めて、そのような手術はギリギリ可能になります。しかしそういう方が合併症を起こしてしまうと、がんセンターにはその方面の専門家がいなかった。例えば心筋梗塞や不整脈が起こったときには、別の医療機関に救急車で搬送していたのです。私は2008年に順天堂大学に移りましたが、このような事態は起こりません。順天堂はそうした例を受け入れる、集学的治療施設なのです。
以前は医師一人当たりの患者さんの数が、圧倒的に市中病院と大学病院、そしてがんセンターとでは違い、手術のクオリティにも大きな差がありました。しかし合併症への対応力は、大学病院の方がある。私はがんセンターのやり方をそのまま順天堂大学にもってきて、順天堂大学の総合力と合わせました。こうすることで、がんセンターよりも良い治療が実現できると確信したからです。
順天堂大学では年間1500例を目標に掲げています。おそらく来年には800件にはなると思います。しかし量と質はある意味で反比例しますから、どこかで臨界点は来ます。今のメンバーでできるのはここまでということはあり、それが800件かと。がんセンターに何人かレジデントを出しているので、彼らが帰ってきて現スタッフのレベルに達することができれば、1500件という数字は達成できると思っています。われわれが身をもって示し、一定の評価を受ければ、おのずと他の施設も追従してくるでしょう。私はそういう「革命」を起こしたいのです。
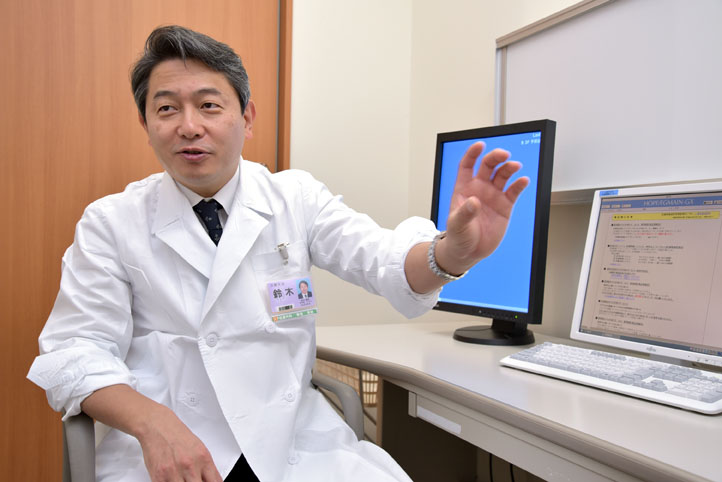
──「優れた医師」になるためには何が必要だとお考えでしょうか。
鈴木 今の世はデジタルですが、デジタルよりもアナログの方が情報量は多いのです。まずは患者さんのそばに行き、手を触り、脈をとってみましょう。たとえ血圧が130でも、しっかりした脈や弱い脈は数字に出てきません。
弱波と強波、手の温度、血の巡りといった「連続変数」は、いま数字で全部出るので、若い人はとかくこれらを真っ先に報告しがちですが、これらは基本的にデジタルで、情報量が限られています。要は患者さんが元気なのか、そうでないのか。若い頃にそうしたことを意識して日々トレーニングしていれば、どんなに検査値がおかしくても会ったときに「ああ、大丈夫だ」と、パッと分かるのです。
剣道には「遠山の目付」という言葉があります。手術では一点を見ず、遠くの山を見る感覚がとても大事です。患者さんの胸の中はもちろん、麻酔やモニターの音も全部聞きながら、オーケストラの指揮者みたいに振る舞うのが理想です。
──信頼できる施設や医師を探す際の基準についてお聞かせください。
鈴木 呼吸器外科では手術のクオリティがそのまま患者さんのQOL(生活の質)と予後に直結します。このご時世、間質性肺炎などを合併した方などで手術がうまく行かずに命取りになってこじれてしまう可能性は非常に高く、そうすると医師側が萎縮し、手術を避ける事態が起こりがちになります。
私たちは、さまざまなリスクの説明をし、リスクを取るのに自分たちも患者さんも一定の感覚で同意できれば、どんなに危険な手術でも行うようにしています。面白いことに、そういうギリギリのところでお話しした手術はほぼうまくいくのです。そこを支えるのは、やはり信頼関係ということになります。