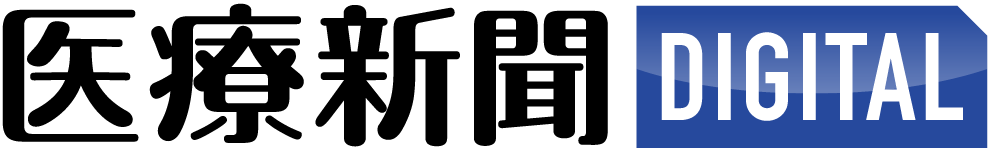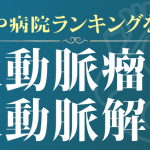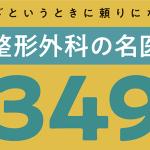投稿日: 2017年10月31日 9:54 | 更新:2017年11月1日10:25

培ってきた経験と高い技術で
ライフワークとなる肺移植に臨む
日本で初めて生体肺移植を成功させ、数多くの症例に携わってきた伊達洋至医師。
肺移植手術の第一人者として「量、質、スピード」をモットーに掲げ、
妥協のない優れた手術に向け、日々邁進している。
■取材
京都大学大学院医学研究科器官外科学講座
呼吸器外科学教授
伊達 洋至 医師
2007年に「肺がん治療の発展」「肺移植の再開」という二大使命を帯び、京都大学呼吸器外科教授に就任した伊達洋至医師。自身の累計症例数は肺移植と肺がんを合わせ3500例以上、年間に担当する症例数は120例ほど、同院呼吸器外科全体で見た場合、手がける症例は年間500例以上を数える。
まず、伊達医師が肺がん治療で特に重視して取り組んでいるのが、超早期肺がんと進行性肺がんの2つであり、それぞれ別の難しさを持つという。数㍉から1㌢の超早期肺がんでは、往々にして病変の位置が不明確となりやすい。肺を覆う胸膜近くに腫瘍があれば触診や視診ですぐに分かるが、少し奥になるだけで難易度が上がってしまうのだ。そこで、CT画像で得られた病変の位置を正確に把握するために、伊達医師らは気管支鏡で、体の内側から肺の表面に色を付ける「マーキング技術」を独自に開発したという。「外側からのアプローチではまれに空気が入り、重篤な状態になる危険があります。それを避けるための方法です。その上で、小さな傷ですむ胸腔鏡を使用し、病変を切除します」
一方、進行性肺がんでは手術、抗がん剤、放射線などを組み合わせる集学的治療が中心となる。特に心臓近くの大血管や骨に食いついている腫瘍は、従来は手術が難しいとされてきた。ここで要求されるのは、腫瘍切除後に血管をつなげる技術や、削った後の骨を支える技術だ。「非常にリスクの高い、時間もかかる大きな手術ですが、われわれの施設では積極的に取り組んでいます」

もう一つの大きな使命である肺移植は、伊達医師にとってライフワークと言えるものだ。1984年に岡山大学医学部の大学院に進み、88年の修了まで研究していたテーマもまた肺移植。その頃、世界で初めて肺移植を成功させたのが、当時アメリカ・トロント大学に在籍していたクーパー医師だった。89年、最初のアメリカ留学で、ワシントン大学の研究生として、当時同大学に移っていたクーパー医師の指導を受ける。一旦帰国し、93年から95年まで再渡米。93年から94年まではクリーブランドクリニック、その後は再びワシントン大学にフェローとして在籍し、同大胸部外科肺移植ディレクターであるパターソン医師の下、臨床経験を積んできた。「パターソン医師はトロント大学時代にクーパー医師の下で勤務していた方。ご一緒に肺移植をされており、まさに両巨頭的存在。この両先生に教わることができたことはすごく幸運でした」と伊達医師は振り返る。
95年に帰国した伊達医師は、98年に岡山大学で日本初の生体肺移植に成功する。「患者さんは24歳女性。その頃の私は助手(現・助教)で39歳。でも実際にアメリカで肺移植を経験している日本人は、私以外にいませんでした。当時の同大呼吸器外科教授である清水信義先生が、私を信頼して自由にさせてくれたのです。感謝と同時に、上に立つ人間がどうあるべきか学んだのもこの時でした」。京都大学に着任したのも、日本で最も多くの肺移植に携わってきたという実績を見込まれたからだ。同大学では2006年に両肺移植を受けた患者が重篤な脳障害で亡くなったことで肺移植を自粛していた。伊達医師が中心となって、新しいチーム体制やマニュアルを作り上げたことで、生体肺移植は2008年、脳死肺移植は2010年より、再開を果たすことができたという。
肺移植の難しさについて、伊達医師はこう語る。「まず、術中術後の管理の難しさがあります。心臓や肝臓が基本的に形を変えないのに対し、肺は膨らんだり縮んだりと、形や大きさが変わる臓器なのです。手術時の肺はしぼんでいますが、それが術後、膨らんだ時にどうなるかをイメージして血管や気管支をつなぐ必要があります」。加えて、心臓や肝臓であれば移植後は外の世界から完全に遮断されるが、肺は常に外気に接し、汚染物質とも接触する可能性が高い。50種類ほどの細胞の集合体であることから拒絶反応及び免疫反応も起こりやすいのも問題だ。「すなわち、免疫機能を抑制しながら、患者さんへの細菌感染をいかに防ぐかが重要になるのです」
伊達医師は自身の教授室の机の上に木綿の布と針、糸を常時置いており、暇な時に血管を吻合する練習をしているという。がんと違い、肺移植は組織の切除だけでなく、移植後の吻合も重要な要素となる。心臓と肺をつなぐ肺動脈は血流量が多い一方、血管壁がきわめて薄い。そうした繊細な血管を的確につなぎ、肺の機能を維持するために求められる技術は、こうした日々の修練が支えているのだろう。「この練習は、2週間に1回の頻度で行われている肺移植手術の前日もしくは当日朝にも必ず行っています。手を動かしておくことで自分の気持ちを落ち着かせ、安心して手術に臨めるのです」
加えて現在では、手術の精度を高めるために、先進技術も活用するようになった。例えば、2014年に手掛けた手術では、3Dプリンタが大きな役目を果たしている。「その時、特発性間質性肺炎で左肺移植を必要とする40代の女性の方に、同年代であるご主人の右肺の一部を移植しました。このような手術では普通、左肺を使いますが、それではサイズ不足だったのです」。人間の左胸には心臓があるため、左肺下部分が小さい。対して右肺下は心臓がないので若干大きく、サイズを何とか満たす。しかしこの場合肺をひっくり返す必要があり、血管や気管支をすべてうまく縫えるかが課題だった。
そこで伊達医師らは、患者とドナーのCT画像を使い、3Dプリンタを使用して模型を作成。術前にシミュレーションし、「こう縫い付ければこうなる」という既視感をつかんだ上で本番を迎えた。「CT画像だけだと、画面に立体構築はできますが、画面そのものは2次元。しかし立体模型なら、3次元で感覚がつかめます。自信もつきますし、手術中に悩まなくてすみます」。通常の生体肺移植では肺静脈を左上葉静脈につなぐが、この手術では心臓の左心耳につないだという。気管支も通常の主気管支ではなく、上葉気管支につないでいる。こうした複雑な手術ができたのも3Dプリンタを活用したからだ。

3Dプリンタで作製したという、肺の実物大立体モデル
──手術もマラソンも結果を決めるのは
本番までの戦略とトレーニング量──
伊達医師は、後進の育成への取り組みを、今後の目標として真っ先に掲げる。「アメリカと日本、それぞれでの恩師との交流のおかげで今があることは確かですから。いま当施設にいる臨床医、大学院生など31名のスタッフに、私の持っている経験や知識、技術を可能な限り伝える。それが、今の私の仕事でもあります」
そんな伊達医師は、高校で陸上競技中距離のインターハイ強化選手に選ばれた経歴を持つ。その後マラソンに転向し、3時間を切るタイムも何度か達成している。現在も毎朝1時間ほど走り、月間300㌔をこなす。「マラソンはスタートまでの準備――練習量や体調維持で勝敗が決まりますが、手術も同様で、技術が突然向上することはありません。本番までにどれだけ戦略を練りトレーニングを積むかで結果の良し悪しが決まるのです」
最後に伊達医師は「ランナーとしては、サブスリー達成をもう一度。そして2018年2月の別府大分毎日マラソンにはぜひ出たいですね」と快活な笑顔を見せてくれた。