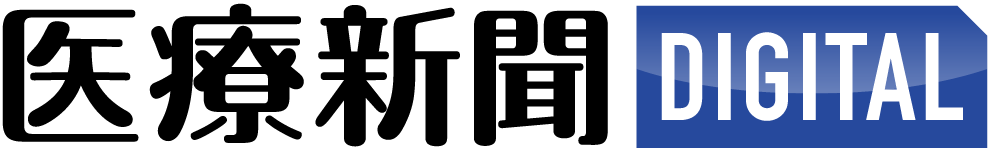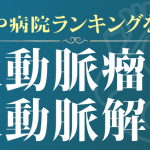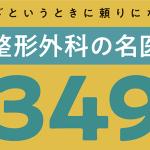投稿日: 2024年7月7日 20:00 | 更新:2024年7月8日12:00

各領域のプロフェッショナルである「名医」へ、その生い立ち、医師になったきっかけ、実績、そして未来へのメッセージをインタビュー。
一般生活者へ最新医療を啓蒙、医師へのメンタルブロック解消により病院や医師選びの選択肢の拡大を実現し、個々にとっての最適な医療の受診につなげることを目的にしています。
一般生活者へ最新医療を啓蒙、医師へのメンタルブロック解消により病院や医師選びの選択肢の拡大を実現し、個々にとっての最適な医療の受診につなげることを目的にしています。
3人目は乳がん治療におけるプロフェッショナル 大野真司先生(相良病院 院長)です。
7回にわたるシリーズの3回目は「医師になってからの軌跡(前編)」になります。
7回にわたるシリーズの3回目は「医師になってからの軌跡(前編)」になります。
第3回:食道外科医から大腸・乳腺グループへ
最も大変な領域である食道外科医を志す
—研修が始まった頃はいかがでしたか。
研修が始まった頃、父が肝臓病で亡くなったこともあり、肝臓外科を目指していました。当時、外科には16人の研修医がいて、8人が大学病院で、もう8人が地方病院で1年ずつローテーションを行っていました。
研修当初は、自分の考えて行動することがそのまま目の前の患者さんの治療結果に繋がるので、「こんなに楽しい仕事でお金をもらえるなんて幸せだ」と感じていました。しかし、後になってそれが自己満足だということに気付き改めました。
—食道外科医に進まれます。
私の担当指導医は食道外科の専門家で、多くの食道がん患者を担当していました。食道がんの患者さんは術後に1週間ICUに入りますが、合併症が発生したり再発することも多く、いつも緊迫した状況でした。今でこそ多くの治療法が確立していますが、当時は治らないことも多く、亡くなる際に感謝される患者さんや、もうこれ以上治療しないでほしいと言われる患者さんもいました。
必死に治療に取り組んでいた自分が、実力不足故の自己満足に陥っていることに気付きました。そうした中で、私は外科の中でも難易度の高い領域の一つである食道外科を志すようになりました。当時の教授からも勧められて、3年目から食道外科医を専攻し、5年目まで研究に励みました。

今に活きているボスとの2年4か月
—テキサス大学での留学について教えてください。
私は米国テキサス州のテキサス大学腫瘍学部門で、リサーチフェローとして2年4か月間留学しました。そこでは、プラチナ製剤のシスプラチンやカルボプラチンと温熱療法の組み合わせに関する動物実験(in-vivo)や細胞実験(in-vitro)を行っていました。

研究結果としては、いくつかの論文を発表することができました。ただし、現在ではこれらの治療法はそれほど臨床で使用されていません。しかし、日本に戻った頃は、食道がんや直腸がんに対してこの温熱療法を実際の治療法として用いていたため、この時の研究がその後の臨床にも活かされたと思います。
—当時のボスから大きな学びがあったそうですね。
私のボスは非常に強く、しかし優しくきめ細かな女性でした。当時の日本では女性の社会進出が十分ではなく、女性医師も少なく、責任ある立場に就いている女性も少なかったため、女性のリーダーシップを間近で経験することができました。この経験は、現代の女性の社会進出を理解する上で非常に貴重でした。
女性のボスから学んだリーダーシップや、海外での研究経験は、現在の臨床や研究活動に大いに役立っています。特に、女性の社会進出が進む現代において、その経験は非常に生きています。

九州がんセンターにて本格的に臨床スタート
—テキサス大学から日本に戻った経緯を教えてください。
テキサス大学でのリサーチフェローとしての期間は2年4か月という期限がありました。また、将来研究者になるつもりはなかったため、期間終了後に日本に戻ることにしました。
—九州がんセンターでの勤務はいかがでしたか。
国立病院九州がんセンターでは消化器外科医として1年3か月勤務しました。研修医、研究生、大学院留学と続いていたので、臨床に専念したのはこの1年3か月が初めての経験でした。
ここでの主な業務は手術でした。術者として手術を行ったり、助手として先輩医師のサポートをしたりしました。先輩医師からの指導を受けながら、多くの手術経験を積むことができて、消化器外科医としての基礎を築きました。
当時印象的だったのは、国立病院対抗の野球大会です。この大会は平日の昼に開催されており、医師、薬剤師、事務員など多くのスタッフが参加していました。今では考えられないことですが、病院業務より野球大会が優先されることがあり、その当時の病院の雰囲気を象徴するエピソードとして記憶に残っています。

大腸・乳腺グループでの苦闘の日々
—九州大学医学部附属病院では大腸・乳腺グループにに移られます。
九州がんセンターで1年ほど勤務した後、教授から大学に助手として戻るようにと言われ、九州大学医学部附属病院の第二外科へ移ることになりました。食道外科医として戻ったつもりでしたが、胃グループに配属され、胃と食道の間にある食道胃接合部の研究も担当することになりました。
1年後、大腸・乳腺グループを担当していたグループ長が大分へ移動することになり、私がチーフを務めるように指名されました。このポジションで2年間務めましたが、手術の経験が十分でないままチーフとなり、多くの手術を任されました。当初は、縫合不全などによる合併症を起こしてしまい、大変な苦労を経験しました。
そこで、数か月間、術者から離れて先輩医師の手術を見学していたところ、自分と先輩医師の縫合の仕方の違いに気付きました。私はしっかりとくっつくように、きつく結んでいましたが、先輩医師はあまりきつく結ばず、適度な強さで縫合していました。私の結び方では逆に血行不全を起こしていることが分かりましたが、この経験から、物事は直球勝負ばかりではだめだと気付ききましたし、適切な塩梅の重要性を知り、それ以降は合併症が減っていきました。
大腸・乳腺グループ長としての2年間が終わった後、食道がんのチーフが群馬大学へ移動することになり、私は食道がんのグループに戻りました。そこで3年間ほど食道がんの治療に従事しました。
—4回目は「医師になってからの軌跡(後編)」になります。
【関連情報】