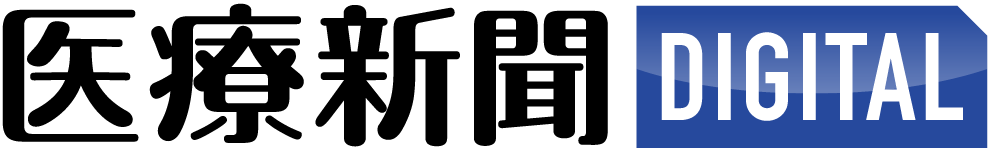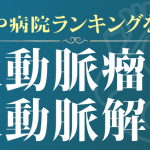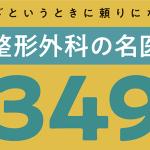投稿日: 2024年7月8日 12:00 | 更新:2024年7月9日12:00

各領域のプロフェッショナルである「名医」へ、その生い立ち、医師になったきっかけ、実績、そして未来へのメッセージをインタビュー。
一般生活者へ最新医療を啓蒙、医師へのメンタルブロック解消により病院や医師選びの選択肢の拡大を実現し、個々にとっての最適な医療の受診につなげることを目的にしています。
一般生活者へ最新医療を啓蒙、医師へのメンタルブロック解消により病院や医師選びの選択肢の拡大を実現し、個々にとっての最適な医療の受診につなげることを目的にしています。
3人目は乳がん治療におけるプロフェッショナル 大野真司先生(相良病院 院長)です。
7回にわたるシリーズの4回目は「医師になってからの軌跡(後編)」になります。
7回にわたるシリーズの4回目は「医師になってからの軌跡(後編)」になります。
第4回:乳がん治療のエキスパートへの道
学ぶチーフから創出された一体感
—九州がんセンターに戻られます。
1999年末に国立病院九州がんセンターの乳腺科部長で、日本の乳がん治療を牽引してきたレジェンドの一人が退職されました。当時、私は九州大学で乳がん治療を担当しており、教授からの指示を受けて九州がんセンターに移ることになりました。
—九州がんセンターでの乳がん治療についてお話しください。
最初のうち、一時的に乳がん治療を担当するだけで、食道がん治療など消化器に戻るものだと思っていました。しかし、2年ほど経ったころ、教授から先輩医師を介して「なんで乳がん治療を必死にやらないんだ」と叱られました。その時、自分が置かれている状況に対して全力を尽くしていなかったことに気付きました。
その叱責を受けて、甘さを反省し、「これから一生乳がん治療をやるんだ」と腹を据えました。放射線技師にマンモグラフィーの使い方を教えてもらったり、病理や超音波の技術を学んだりしました。また、部下の乳腺外科医も私より経験豊富な人が多かったので、彼らからも多くのことを教わりました。
チーフでありながら学ぶ立場で、次第にチームとして一体感が生まれました。フラットな関係を構築し、互いに教え合いながら治療に取り組むことで、強いチームが形成されました。この経験を通じて、全力を尽くすことの重要性と、チーム医療の大切さを改めて実感しました。

20年サイクルでの世代交代、次世代を担う
—2000年頃から、乳がん治療には大きな変化があったとのことですが、詳しく教えていただけますか。
初期の乳がん治療は、単に腫瘍を切除するだけで、消化器外科(もしくは外科)が担当していました。しかし、乳がんの患者さんが増えるにつれて、90年代後半には乳がん部分切除で美しく手術することが求められるようになりました。
さらに、2000年頃からは、薬物療法も盛んになり、エビデンス重視の治療に変遷してきました。また、患者さんが乳がんに関する多くの情報を持つようになり、消化器外科での兼務は難しくなってきました。このため、乳がん治療は専門的に行う時代になりました。
ちょうどその頃、乳がん治療を牽引してきた先生方が引退するタイミングでした。20年間隔で世代交代があり、私を含めた40代の医師たちが次の世代を担うことになりました。その中には、現在乳がん治療の第一線で活躍している中村清吾先生、戸井雅和先生、野口眞三郎先生、岩瀬拓士先生、岩田広治先生などがおられました。
私たちは、お互いに切磋琢磨しながら、日本の乳がん治療を世界に追いつかせよう、そして追い越そうと努力していました。その過程で、多くの知識や技術を共有し合い、共に成長してきました。乳がん治療の専門家として、患者さんに最良の治療を提供するために、日々研鑽を積んでいました。
乳がん診療にてコミュニケーションの真髄を知る
—乳がんの患者さんに対するインフォームドコンセントでご苦労があったそうですね。
乳がんを診るようになって、コミュニケーションの大切さを痛感しました。食道がんや胃がん、大腸がんの患者さんに対しては、インフォームドコンセントは問題なくできていたんです。多くの場合、おじいちゃんが患者で、子どもたちも立派な成人で50歳前後、孫もいる状況でした。子どもが常に横についていてしっかりしており、奥さんも高齢だったりするので、治療に関する質問がほとんどありませんでした。
しかし、乳がんの患者さんに30分ほど説明した後に、「わかんないことありますか」と尋ねると、「私は乳がんですか」とか、「手術が必要ですか」、「助かりますか」といった質問が返ってきました。その時は「だから今説明したように・・・」と返してしまうことがありました。どうしてこんなに理解してもらえないのか、消化器の患者さんたちはよくわかってくれたのにと思っていました。今考えると「だから外来」でしたね。
1年間くらいその状況が続きました。ある患者さんから「すぐに入院しないといけないですか」と聞かれ、「だから・・・」と返そうと思ったのですが、その時初めて「どうしてですか?」と聞いたんです。すると、「子どもが今度卒業式があって、その後2、3週間後に入学式があるので、これが終わってから入院するわけにはいかないだろうか」と言われました。その時受けたショックは今でも忘れられません。
その瞬間、私が必死に説明していた時、患者さんは一生懸命そういうことを考えていたのだと気付きました。頭が真っ白になるのではなく、私が頭を真っ白にさせていたのだと。人の言葉や話が耳に入ってこない状況を作ってしまっていたのです。
—その後、どのようにコミュニケーションを改善されていったのでしょうか。
九州がんセンターの精神腫瘍科の先生や心理士に心理学を教えてもらい、臨床心理の本を読んだりして、聞くことの難しさやコミュニケーションは技術であり後天的に身に付けられるものだと知りました。それからは言葉の使い方、間や沈黙の使い方を工夫し、こちらから質問をするようにしました。そうすると患者さんが一番気にしていることを聞き出せるようになり、「私、助かりますか」とか「乳房を残せますか」といった質問が出るようになりました。そしてそこから説明していくことで、患者さんとのコミュニケーションが高まり、理解も深まりました。「だから」と言うことはなくなり、「なるほど外来」となりました。
<写真11:大野先生の診察時の写真>
乳がん治療からがん研有明病院の組織改革・運営へ
—がん研有明病院に移られたきっかけについてお話しいただけますか。
がん研有明病院の、前任の乳腺外科部長・センター長は岩瀬先生で、私が九州がんセンター時代に愛知県がんセンターに乳がん治療を1週間学びに行ったときに教えていただいたことが縁となり、私の師匠でもある方でした。岩瀬先生は「岩瀬道場」と呼ばれるマンモグラフィーの写真を部屋中に並べて読影してくれる場で、多くのことを教えてくださいました。岩瀬先生が定年を迎える際、後継者が必要となり、院外から迎えようとなったため、私が指名されました。
—がん研有明病院に移られていかがでしたか。
がん研有明病院の臨床水準は非常に高く、目の前の患者さんの治療に専念していました。しかし、その実績を外部に発信することができていませんでした。九州大学にいた頃から、症例数が最も多いがん研有明病院が症例やデータを発表し、リードしていく必要性を感じていました。そこで、個々の高い技量を持つ医師たちがチームとして活躍する組織にするための仕事を進めました。

乳腺以外でも、がん研有明病院は古い考えややり方が続いているところがありました。私と前後して新しく来た部長5、6人が単身赴任であったこともあり「単身赴任の会」を作り、1、2か月に1回集まってがん研有明病院の課題について議論していました。そこで、がん研有明病院の改革案を考え、実行に移していきました。
その後、私は院長補佐となり、乳腺センターの仕事よりもがん研有明病院を良くする仕事を任されました。病院機能評価の担当として、組織運営の仕事を中心に行いました。「単身赴任の会」のメンバーはいずれも副院長となり、がん研有明病院の改革、改善を続けていきました。
がん研有明病院での経験は、組織運営やコミュニケーションの重要性を改めて実感させてくれました。個々の医師の高い技量をチームとしてまとめることで、より良い医療を提供できるようになり、組織全体の向上を図ることができました。この経験は、今後の医療現場でも大いに役立つと感じています。
—5回目は「私の現在位置と未来について(前編)」になります。
【関連情報】