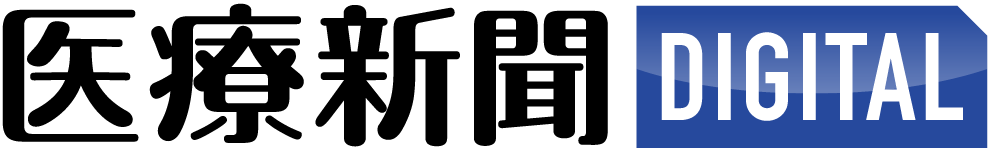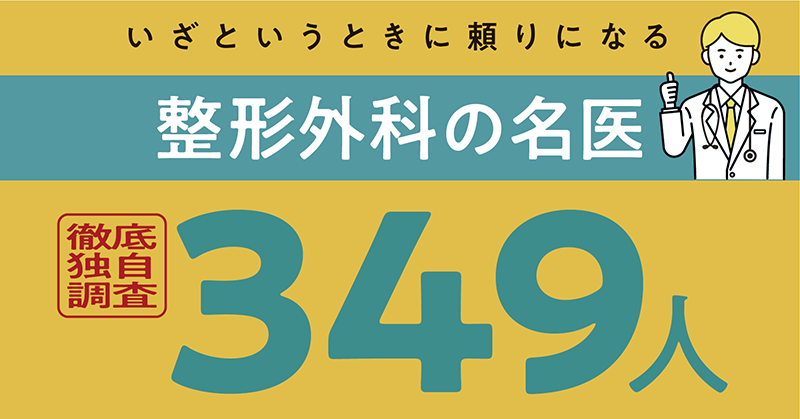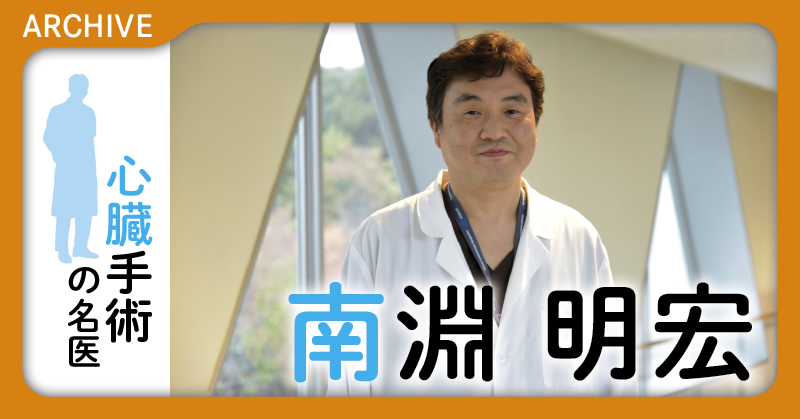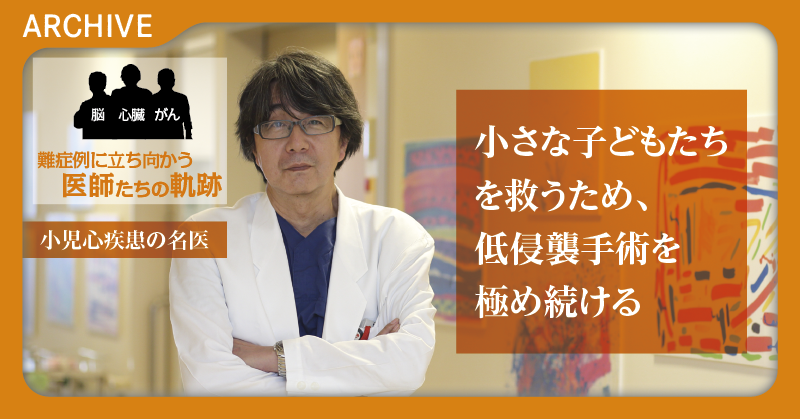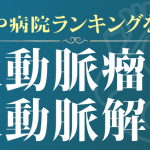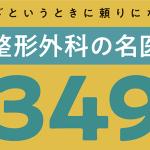投稿日: 2017年2月22日 9:00 | 更新:2024年1月19日14:46

世界をリードする日本の胃がん手術
そのスポークスマンとして海外を回る
日本人の罹患数・死亡数が多いことで知られている胃がん。それだけに、診断・治療技術については日本が圧倒的に世界をリードしている。この、日本で発展してきた胃がん手術を世界に広めることに尽力したのが佐野武医師だ。
■取材
がん研有明病院 副院長・消化器センター長・消化器外科部長
佐野 武 医師
──医師及び今の分野を志したきっかけをお聞かせください。
佐野 実家は大分県の杵築(きつき)市という小さな城下町で、400年間、始祖の佐野徳安(とくあん)から代々医業を営んでいました。私自身、町の人々からも「跡取り」と言われて育ち、それ以外の将来像が描けるわけでもなく、中学生まで自分は医者になるのだろうと漠然と思っていました。高校生になると、さすがに反発心がわき、自分には違う道があるはずだとも思いました。一時は弁護士や教師のような、人を説得する職業もいいかなとも。しかし最終的には親にこんな強く出られたことがないという位に説得され、医師への道を目指すことに決めたのです。
大学に入学してからは、進むとしたら内科と何となく考えていました。親が内科医でしたし、一番多くの病気を診ることができる診療科と思っていましたから。それが、実習で各科を回るうちに「外科はすごい」と思うようになったのです。外科では手術という非常に大きな出来事に皆が集中し、それが終わると患者さんがスーッとよくなって帰っていきます。そのリズムの良さ、ダイナミックさ、そして、内科では「診断して病気がわかったけど治療法がない」ことがあるのに対し、外科の「わからないけどとにかく治してしまう」点にも惹かれました。診断や研究はもちろん大事ですが、実際に手を下して治療する点は、外科の大きな魅力だと思いました。医師になって5年目に専門領域を選択することになり、尊敬する恩師の小堀鷗一郎先生が率いる胃のグループに入りました。
その後、国立がんセンター中央病院に入ります。私が胃がん治療に打ち込んでいるのを知った、先輩である笹子三津留(ささこみつる)先生(当時医長)の誘いでした。がんセンターの魅力は、大学医局を超え、日本中からさまざまな医師が集まり、切磋琢磨しているところ。見たこともない道具の使い方、考え方を見聞きし、「自分は、この広い大海に漕ぎ出す時だ」と感じました。
──日本の胃がん手術のスポークスマンとして海外を回ってきたと聞きました。
佐野 国立がんセンター中央病院では16年を過ごしました。この間、脈々と日本の先達が作り上げてきた「日本スタイル」と呼ばれる定型手術、つまり胃の3分の2以上と、胃の周りにある第1群、第2群のリンパ節を切除する「D2胃切除術」が、海外、特に欧米諸国できちんと理解されていないことを、常々悔しく思っていました。そこで自分でも、これがオーソドックスな方法なのか絶えず自問自答しながら手技を磨きました。同時に、海外の外科医にもきちんと理解してもらうため、来日した見学者が手術中に矢継ぎ早に繰り出す質問に対し、手術の手を止めることなく解説するよう頑張ったのです。そうしているうちに、今度は私が外国での手術指導をするオファーが届くようになりました。

英国外科医師会で手術指導を行う佐野医師
こうしたプレゼンテーションでは「なぜこうしなければいけないか」を説明し、納得してもらう必要があります。そこが一番大変で、私自身、フランス・パリへの留学経験から、欧米人が納得するロジックを考え、工夫を重ねました。ディスカッションにおける欧米と日本との一番大きな違いは、話をする人達が平等で、言葉の上下関係も存在せず、イーブンだということ。そして相手が納得するのを一つひとつ確認しながら、自分の言いたいことに導いていく段階を踏むことです。教授、医師、研修医が、無駄な感情を持たず、何の遠慮もなく話し合う。考え方が異なれば時に怒鳴り合いにもなる。でも会合が終了すると、何もなかったようにあっさり仲良く打ち解ける。彼らに言わせると、ディスカッションやカンファレンスはあくまでその場だけのことであり、あとに引きずるのはルール違反なのです。
──現在目指していること、注目していることはどのようなことですか。
佐野 今、関心を抱き、取り組んでいるのが、ガイドラインや取扱い規約の改定です。ガイドラインは、皆の意見を引き出しながら、科学的根拠に基づく落としどころを見つけ、標準化に向けて策定する必要があります。また世界ではTNM分類(悪性腫瘍の病期分類に使用される指標)が使われていますが、日本は独自の取り扱い規約で運用しています。そこで日本と世界の規約を連携させる作業をここ10年進めており、胃がんに関してはかなりの部分で両者を近づけることができました。
また治療の面では、抗がん剤が胃がんに対してよく効くようになっています。一方、もちろん手術の役割も大きいわけで、手術を最も良い形に収め、かつ抗がん剤との組み合わせで昔は治らなかった病気を治す─これが現在、一番の関心事です。その実現のためには、新薬の効果と副作用を見きわめながら、どのように手術と組み合わせていくかの臨床試験を、きちんと行っていくことが大切です。
画像が高精細になり、他人の手術を映像で見たり、意見を聞いたりする機会も増えました。今まで二千数百例の胃がん手術をしてきましたが、それでもなお新しい発見があります。これは、胃という臓器が周囲との関係も含め、複雑な構造をしているからです。また、手術道具を新しいものにしていくことも大事なことです。今、腹腔鏡手術に使用される道具がものすごい勢いで進化していますが、そうしたエネルギーを開腹手術にも応用させてもらいたいと考えています。
私は腹腔鏡手術への抵抗勢力と考えられていますが(笑)、腹腔鏡手術自体は優れた技術ですし、今後ますます発展の余地があると思います。両手術は、決して対立するものではありません。ただ、従来法でやっていれば問題なかったものが、新しい方法を行ったことで悪い結果となり、不利益を被る人が出るのはよくありません。現在の日本では手術の半数以上が早期がんです。腹腔鏡手術もまずはその病気の治療で安全に技術を磨き、きちんとしたスタンダードができあがった上で、その後もう少し大きながんへの適応を広げていくべきだと思います。
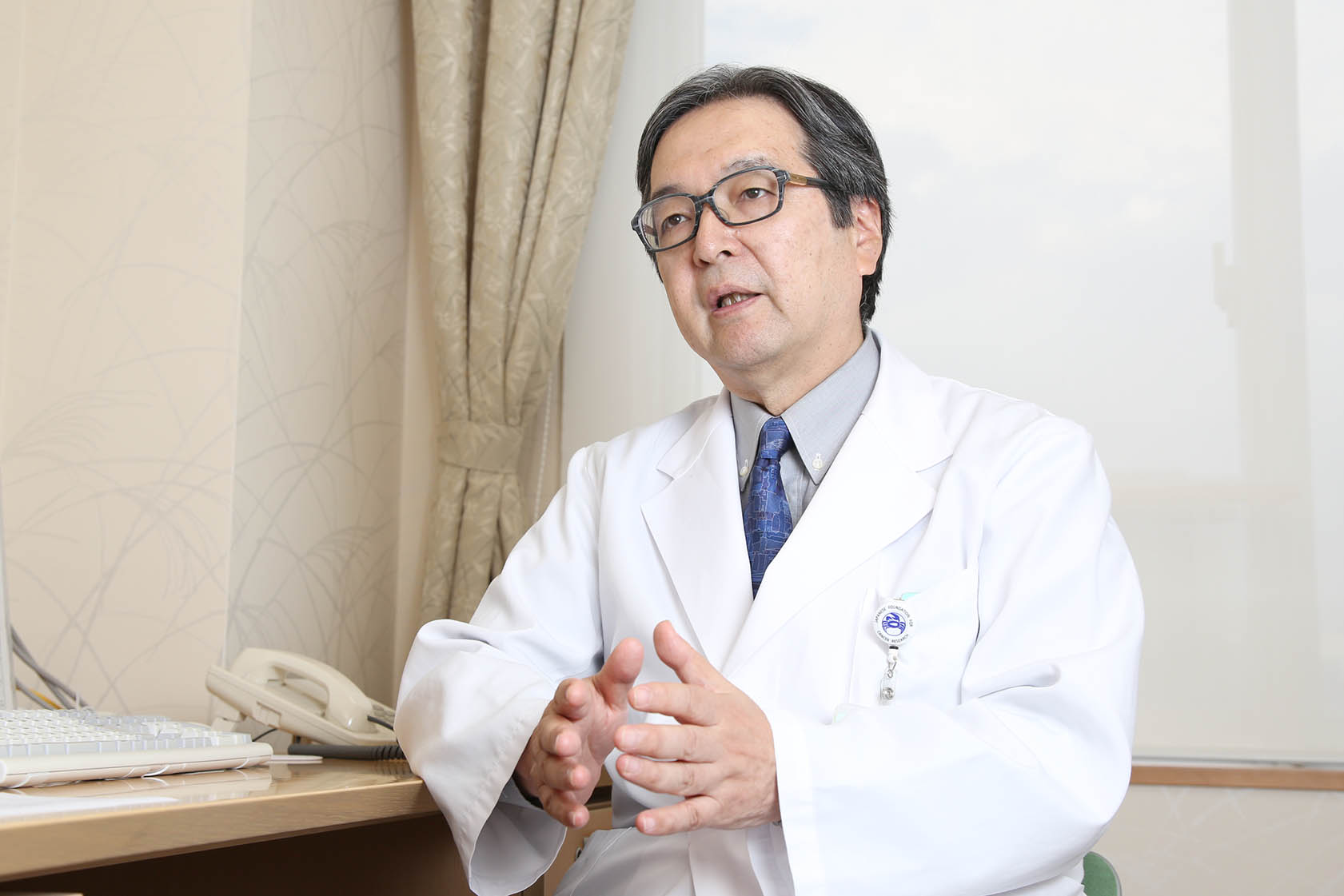
──何を意識して研鑽を重ねてきたのでしょうか。
佐野 まず技術に関わることですが、私は、自分の手術をなるべく映像に収め、自分で短く編集して保存しています。それを後で見返すと、術中意識せずに通り過ぎた部分や、改善点に気づくことが多いのです。若い人も、ぜひ自分の手術を映像にして編集し、後から何回か見返してほしいと願っています。
このような日常の研鑽は当然欠かせませんが、医師の姿勢として、私自身は患者さんに接する際、「この人が自分の父親、母親だったらどうするか」と絶えず自分に言い聞かせるようにしています。そうすることで、自分が今ベストと考える治療を患者さんに提示できると思うからです。
──最後に、信頼できる医師や施設を選ぶ際に注目すべき点について教えてください。
佐野 医師や看護師、またお掃除をしている方など、皆が一生懸命、熱心にやっていると感じられる施設は良い病院だと思います。もちろん、そういうことは現地を見ないとわかりません。正しい情報を得ようとしても、各施設のホームページなどを見るとつい綺麗な写真に惑わされることがあります。がんでしたら多少遠回りでも、国立がん研究センターのホームページにある「がん情報サービス」などで、自分の病気や治療法について知ってから、その治療にふさわしい病院を探すべきでしょう。
そして治療件数はやはり大事です。1つの病気について、数多くの患者さんを診ていて初めてわかることがあると共に、突発的な事態にどの程度対応できるかは、数がものをいうところが確かにあります。欧米では、すでにがん治療、特に手術は専門病院に集約されてきていますが、この流れは今後、日本にも及んでくるのではないでしょうか。