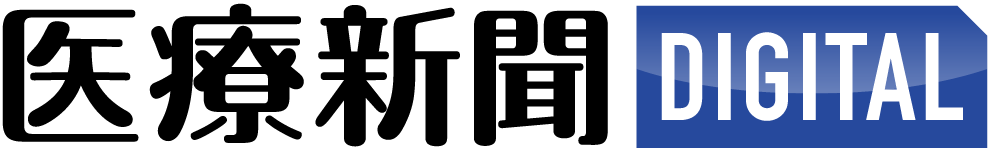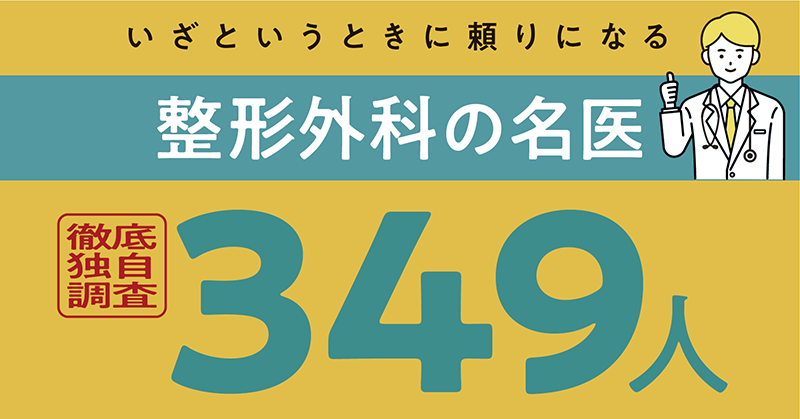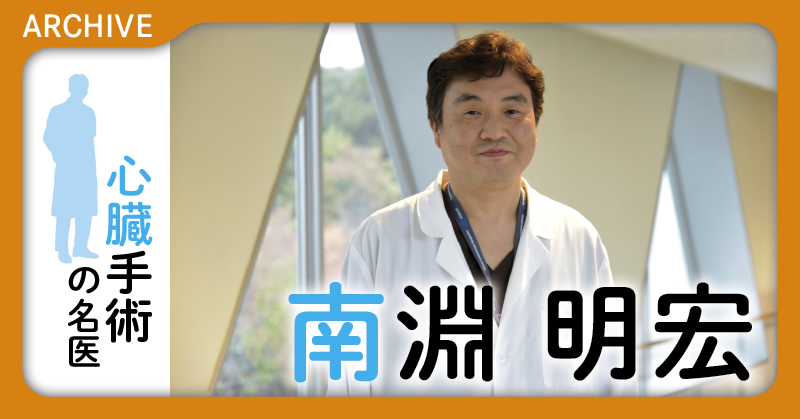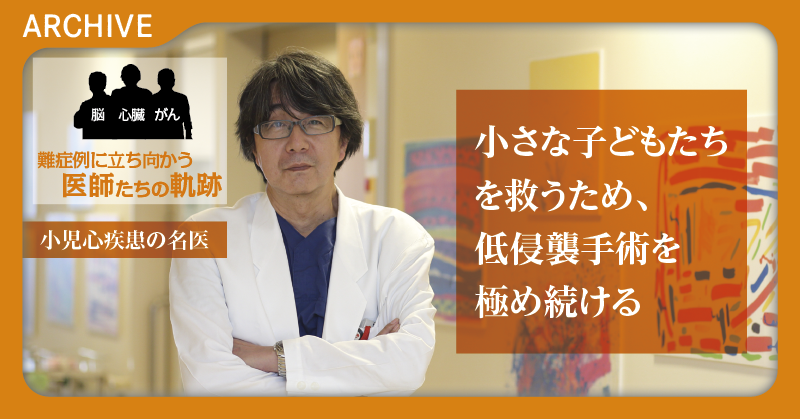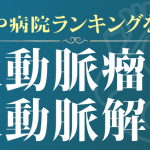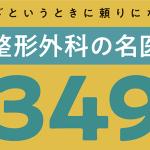投稿日: 2017年3月15日 9:00 | 更新:2024年1月19日14:43
 ”
”
治療における問題点を見つけ出し
解決のためのアイデアを考え続ける
破裂することで生命に関わるくも膜下出血を引き起こす脳動脈瘤。この疾患への治療法として、開頭せずに血管内から病変にアプローチする脳血管内治療が注目されるようになった。同治療の名手であるだけでなく、日々新しい治療の開発にも取り組んでいるのが村山雄一医師だ。
■取材
東京慈恵会医科大学 脳神経外科学講座 主任教授
村山 雄一 医師
実験の場を得る
──脳血管内治療を志した経緯についてお聞かせください。
村山 生まれは東京の駒込です。両親とも医療とはまったく関係のない職業に就いており、親戚にも医師は皆無。ですから誰かの背中を見て……というドラマチックなエピソードはなく、私自身、医学にそれほど強い志を持ってはいませんでした。ただ、高校のときに下半身不随の友人がおり、そのイメージが自分の進路に影響したかもしれません。
東京慈恵会医科大学では色々な科を回る中で、脳や心臓など命に関わる重要な臓器に興味を持ち、特に神経が面白そう、という理由で脳神経外科に入りました。専門分野選択では、侵襲が少ない脳血管内治療という未知の分野に関心をもち、この道に進むことにしました。
私の指導教官だった同大・阿部俊昭教授(当時)はカナダやイギリス、アメリカで経験を積まれており、脳血管内治療の「老舗」であるカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)のフェルナンド・ビヌエラ(Fernando Vinuela)先生とは、一緒に仕事をするなど深い親交がありました。私も単純に海外に行ってみたい気持ちがあり、阿部教授に興味がある旨を伝えていました。1993年、阿部教授が来日中のビヌエラ先生に私を紹介してくださる機会に恵まれ、翌年にはUCLAを見学させてもらい、無給で働かせていただくことになりました。
当時、同施設で生み出されたコイル塞栓術を見学しに、世界中から人が訪れていました。多くの方が見るだけでしたが、脳動脈瘤治療をやったこともない私は「この治療はきちんと塞がらず、再発を起こしかねない弱点がある」と思い、脳動脈瘤を再生医療技術で治すアイデアを話しました。すると「お前は面白いことを言う」と、実験環境を整えてくれたのです。実験で実用化の芽がありそうだという結果が得られ、3年目を迎えて「有給にするから、もう少しここにいないか」と言われました。「臨床がやりたいので日本に帰ります」と答えたのですが、「それなら臨床ができるよう、カリフォルニア州に交渉して、ライセンスを取らせるから」と。
起こった際の対処の準備を
──脳血管内治療医として、どのようにして技術を培ってこられたのでしょう。
村山 当時UCLAで数多い手術を見る機会に恵まれたこと、そして私の行う実験をビヌエラ先生がご覧になったことが、手技の勘所についてのトレーニングになったことは確かです。私が臨床をスタートさせた時も、先生はすぐに手技をやらせてくれました。
手術には、ある程度の器用さも求められますが、それ以上に慎重であることが重要です。即ち、「ここで何かあった時どうする」と常に考え、「今、破れるかもしれない」「詰まるかもしれない」と最悪の状況を絶えず想像し、起こったときの対処の準備をしておくのです。「上手な医師」と言うと、一般には他の医師が3時間かかるところを1時間でやってしまうことなどがクローズアップされがちですが、手術はそういうものではありません。100件、1000件というオーダーの中で出てくる同じようなトラブルをいかに予見し、回避するか。術前計画でも最もリスクが少ない選択肢を選ぶことが大事です。奇をてらった手段や、思い付きで浮かんだ手段は必要ありません。ゴルフに例えれば、ピッチングウェッジでもパターでも、何打でもいいからフェアウェイを外さず、ボールを無くさず刻む、ということになります。
アメリカで医師を何年もやっていると、今度はアメリカの弱点が見えてきました。当時私は放射線科に属していたのですが、術中にトラブルがあった際に手術室で対応すべきところを、画像診断装置のある別室に移動するため、手遅れになってしまうリスクがあったのです。そこから、脳血管内治療は手術室で行うべきと考えるに至りました。しかし、それを脳神経外科と放射線科で壁があった当時のアメリカで行うのは無理。壁を取り払い、手術室でカテーテル手術を行えるハイブリッド手術室のスタートは、日本に戻ってからでした。自分が信じるアイデアやコンセプトが、今の施設では実現できているのです。

チーム内のコミュニケーションも大切にしている村山医師
──現在取り組んでいることや、目指されていること、注目していることについてお聞かせください。
村山 ブレークスルーのためには、テクノロジーと医学の融合が欠かせません。今、開発している新しいステントは、「流体力学を利用して血液の流れを変える」がコンセプトになっています。またスマートフォンを利用した遠隔画像診断治療補助システム「JOIN」は、保険適用となった初めての医療用ソフトウェアとして、エポックメイキングな技術となりました。大切なことは手先の器用さだけでなく、問題解決のためのアイデアとビジョンであり、不要な手術を避けるために、血流解析から脳動脈瘤が破裂する危険性を見極めるコンピュータシミュレーションにも可能性を感じています。
他に、再生医療や電気刺激でリハビリ効果を高め、失われた機能の回復を目指す研究や、悪性脳腫瘍への免疫療法についての臨床研究など、既成の概念にこだわらずに幅広い研究を進めています。
解決に向けた実験や研究に努力できることが必要
 ──「優れた医師」になるためには何が必要だと思いますか。
──「優れた医師」になるためには何が必要だと思いますか。
村山 まず、ヤブ医者にならないために大切なのはジャッジメントができることです。それは、患者さんの状態を悪くしないために最適の方針を決める力だと言えます。さらに超一流になるためには、何が必要なのか。それは手術を見て、その問題点がどこにあるのかを指摘できるということです。どんな名手が行おうと、どんなに定番の術式だろうと、手術には必ず問題点があるものです。
例えば血管内治療で絶えずついて回るのが被曝(ひばく)問題です。学生は医師になる前から、カテーテル治療で被曝は仕方がないものと思い込んでしまっています。現代の医学教育では、そういう固定観念、先入観を抱いたまま、今、行われている治療や、マニュアル化された標準治療を身につけることが求められています。一流の医師とは、そこから問題点を見つけ出し、解決するためのアイデアを考え続け、さらに実現に向けて実験や研究に努力できる人なのです。
──信頼できる施設を探す際に注目すべき点について、どうお考えですか。
村山 例えば脳動脈瘤が見つかった場合、「あなたの頭の中に爆弾があります」という表現もあれば、「あなたの脳の血管には小さなふくらみがあります。ほとんどの場合には問題ありません。でも、ごく一部の方で破れることがあります。現状では、緊急で手術を要する状況ではありません」という表現もあります。また、今にも血管が破れそうな患者さんに「破れそうですよ」とそのまま伝えれば、その言葉がストレスとなって破れてしまうこともあり得ます。このような表現一つにも差は現れるものです。
まずは「患者さんに恐怖を植え付けるような施設ではない」ことが重要だと思います。私は、件数だけでは、その施設のことは分からないと思っています。脳動脈瘤には血管内治療だけでなく、開頭手術も行われます。これらはいわば、右手と左手。どちらが良いということではなく、どちらも最適な治療のための手段にすぎないのです。瘤の形状などにより、それぞれの治療法を選択し、場合によっては他施設を紹介する。施設選びにおいては、そういう視点がきちんとある施設かどうかの見極めも大切です。